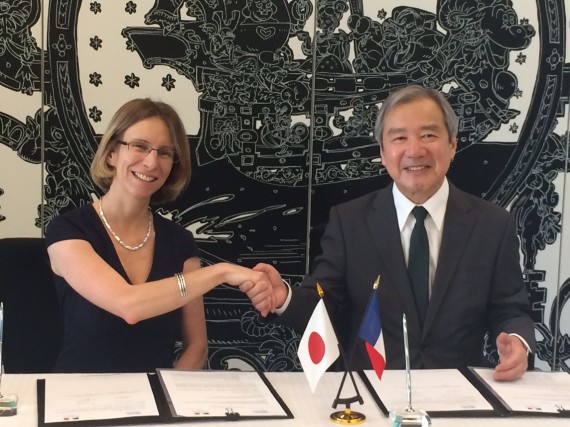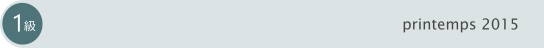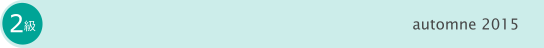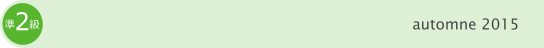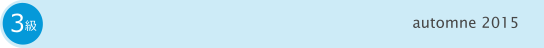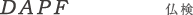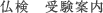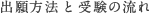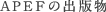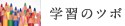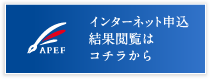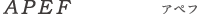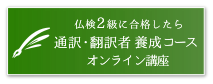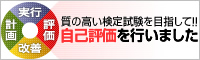長沼 圭一 (愛知県立大学 外国語学部)
私が6年前から勤務している愛知県立大学には外国語学部があり、フランス語専攻が存在している。高いモチベーションを持ってフランス語を学んでいる学生も少なくない。そのため、仏検については、強制されずとも、毎年それなりの数の学生たちが出願し受験していた。そこで、学生たちの受験状況を把握したく、私は愛知県立大学の頭文字をとってAKDの名前でAPEFさんに団体受験の登録を申請した。団体受験と言っても、会場提供や一括申込のような大掛かりなことはせず、個別に申し込む学生たちに団体コードを願書に書いてもらい、合否の通知が私のところに届くようにしたというだけであった。
私がこの大学に赴任した当初、私が所属するところは「フランス学科」という名称であり、10名の日本人教員がいた。ところが、その翌年、新カリキュラムの導入に伴い、「ヨーロッパ学科フランス語圏専攻」という名称に変わった。それまでの「フランス学科」、「スペイン学科」、「ドイツ学科」がまとめられ、「ヨーロッパ学科」となったのである。その際に、ヨーロッパ学科の3専攻は教員の定員を1名ずつ削減され、9名となった。さらに、この新カリキュラムが導入されて5年経った今年、また新たなカリキュラムが導入されることになった。5年前と同じようにヨーロッパ学科の3専攻は教員の定員がさらに1名ずつ減り、8名となった。そのうえ、今回は学生の募集定員も50名から45名へと削減されたのである。なぜ、こんな風にヨーロッパがどんどん縮小されてしまうのか。
これは全国的な傾向であるように思われるが、現在の大学では実利的な部分ばかりが求められているのではないであろうか。現在の世界の経済成長は、アジアにおいて著しいものがある。したがって、今後は大学でも中国や東南アジアに関する学問を提供する場を拡張していくことが必要だと考えられ、相対的にヨーロッパの需要は少ないという判断なのであろう。しかしながら、これについては2つの疑問の念を禁じえない。1つは実利と学問を同じ土俵に乗せてよいのかという疑問である。学問というのは、利益と結びつかなければやる意味がないのであろうか。人は知りたいことがあるからこそ真実を追究し学問にいそしむのではないのか。ヨーロッパで長い年月を経て培われてきた英知をそんなに簡単に切り捨ててよいものであろうか。知を愛することこそが学問の本質ではないのか。もちろんこれが理想に過ぎないことは私もよく理解していることであり、実利的な目的で学ぶことを否定するつもりはない。しかし、これをよしとしたならば、2つ目の疑問が湧くことになる。今後経済成長が期待されるのはアジアだけであろうか。もっと長い目で世界を見れば、アフリカの経済発展は無視できないはずである。フランス語はヨーロッパだけで使用されている言語ではなく、アフリカにはフランス語を公用語とする国が21ヶ国あり、通用語も含めれば29ヶ国にのぼる。本当に実利主義をとるつもりならば、大学におけるフランス語教育を縮小するのは決して得策とは言えないではずである。では、フランス語をいつ学ぶのか。
そんな中、本学では、文部科学省のグローバル人材育成推進事業に申請していたプロジェクトが採択され、2012年度後期からこのプロジェクトが始動した。このグローバル人材育成推進プロジェクトの一環として本学に誕生したのが、iCoToBa(多言語学習センター)という語学学習スペースである。この名称の由来であるが、iには、愛知県立大学の「愛」、I(わたし)、independent(自主性のある)の「i」、Coには、communication(コミュニケーション)、community(共同体)、cooperation(協同)の「co」、Toには、格助詞の「と」、to(~へ)、together(一緒に)の「to」、Baには「場」といった意味が込められており、「愛知県立大学においてコミュニケーションによって世界とつながる場」というコンセプトで新設された。このiCoToBaには英語2名、フランス語1名、スペイン語1名、ドイツ語1名、中国語1名、合計6名のネイティブ教員が配属されている。ネイティブ教員は、大学の正課には組み込まれていないiCoToBa独自の授業を担当する他、iCoToBa施設内のラウンジでの学生とのフリートーク、各種イベントの企画・運営なども行っている。また、iCoToBa施設内には、パソコンを使ってe-Learningができるスペースや大画面テレビで外国語放送やブルーレイ・DVDが見られるスペースも用意されている。
また、グローバル人材育成推進プロジェクトの一環として2013年度後期から実施されたのが、語学検定試験の受験料負担制度である。当初は外国語学部の学生全員分を負担することを目指していたが、結局は予算の都合で2年生と4年生のみが対象者となり、秋季のみ補助されることとなった。仏検については、フランス語専攻の4年生は準1級を、フランス語専攻の2年生は準2級を、第二外国語としてフランス語を履修して2年目の学生は3級を、大学側の受験料負担のもと、受験することが義務付けられた。当然のことながら、これまで学生が自分の意志により私費で受験していたときと比べ、圧倒的に受験者の数は増加した。これに伴い合格者の数も増加したことは言うまでもない。例えば、準1級は私の記憶では以前は毎年1人合格者がいるかどうかという程度ではなかったかと思われるが、今回の2013年度秋季では12人の学生が合格となった。正直なところ、これは私の予想を上回る嬉しい誤算であったが、今後仏検の団体受験が学生にとってフランス語習得のモチベーションを上げるよいきっかけとなり、さらには大学におけるフランス語の復権につながることを期待したい。

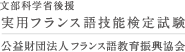
 また、長年、公立や他の私立高校で1年間または2年間選択科目として教えてきた私としては、数年前本校で仕事を始める際、3年間続けて教えられるということで今までとは違う様々な可能性を感じていた。しかし、実際にはクラス全員、30数名の生徒を相手に語学を教えることは簡単なことではなく、3年生ともなると仏検3級取得者から、動詞の現在形もおぼつかない生徒が同じ教室におり、上位層の生徒を伸ばし切ってやれていないということが悩みだった。それを解決するには、必修でなくとも選択で興味のある生徒との小人数クラスにしてもいいのではないかという思いも少し持ち始めていた。
また、長年、公立や他の私立高校で1年間または2年間選択科目として教えてきた私としては、数年前本校で仕事を始める際、3年間続けて教えられるということで今までとは違う様々な可能性を感じていた。しかし、実際にはクラス全員、30数名の生徒を相手に語学を教えることは簡単なことではなく、3年生ともなると仏検3級取得者から、動詞の現在形もおぼつかない生徒が同じ教室におり、上位層の生徒を伸ばし切ってやれていないということが悩みだった。それを解決するには、必修でなくとも選択で興味のある生徒との小人数クラスにしてもいいのではないかという思いも少し持ち始めていた。 そして、2013年度の秋は、高1も今まで以上に多くの生徒が5級にチャレンジし、高2高3で、4級、3級を受験する生徒達も少しずつ増えてきている。また、3年間学ぶとはいえ、前述したとおり3級を取得するのは授業外での生徒本人の相当の努力が必要なのが現状だが、たとえ5級であっても、日本のほとんどの高校生が英語のみを学んでいる中、他言語の資格を取得したということは高校生にとっては優越感や自信という意味を見出し、その後の学習へのモチベーションアップへつながっていくのだ。
そして、2013年度の秋は、高1も今まで以上に多くの生徒が5級にチャレンジし、高2高3で、4級、3級を受験する生徒達も少しずつ増えてきている。また、3年間学ぶとはいえ、前述したとおり3級を取得するのは授業外での生徒本人の相当の努力が必要なのが現状だが、たとえ5級であっても、日本のほとんどの高校生が英語のみを学んでいる中、他言語の資格を取得したということは高校生にとっては優越感や自信という意味を見出し、その後の学習へのモチベーションアップへつながっていくのだ。
 大学の3年生になるまで、つまりは去年の春の時点まで、私はフランス語を学習したことがありませんでした。
大学の3年生になるまで、つまりは去年の春の時点まで、私はフランス語を学習したことがありませんでした。 フランスが主催している国際大会であり、レースの特徴としては
フランスが主催している国際大会であり、レースの特徴としては  とはいうものの、走ってみるとやはりレースは過酷で、一日目から脱水症状に陥ってしまいました。暑さで内臓がやられ、体内の水分も尽きて汗すらかけず、いくら水を飲んでも、いくら塩のタブレットを飲んでも頭痛と吐き気が止まりませんでした。しかしそんな時、一人のランナーが私に声をかけてくれたのです。その人は初老の、紳士然とした男性で、ゼッケンの国籍欄にはFRANCEの文字がありました。声をかけてくれたといっても、その時の私には彼の話すフランス語が理解できなかったのですが、彼はどうやら「水を飲め、一緒に走ろう。」と言っているようでした。彼に励まされ、私は再び走りだすことができました。そうして結局、彼はその日のゴールまで私のことを気遣いながら併走してくれたのです。道中、初めてのフランス語に触れた私はなんとか片言の英語で彼との会話を試みたのですが、あまり上手くいきませんでした。その時、フランス語の簡単な挨拶だけでも勉強しておけばよかったと激しく後悔したのですが、ただ、彼の方は終始鼻歌を歌っていて、そんなことはちっとも気にしていないようでした。サハラマラソンのランナー達は、どこか通じるものがあります。日本から参加していたメンバーとは話が合い、直ぐに仲良くなれました。ならば、あの陽気なフランスの男性とも、もしも私があの時彼が話す言葉を話せていれば、何事かを語りえたはずです。そしてそのように考えると、せっかくのかけがえのない、大切な機会を取り逃してしまったように感じたのでした。
とはいうものの、走ってみるとやはりレースは過酷で、一日目から脱水症状に陥ってしまいました。暑さで内臓がやられ、体内の水分も尽きて汗すらかけず、いくら水を飲んでも、いくら塩のタブレットを飲んでも頭痛と吐き気が止まりませんでした。しかしそんな時、一人のランナーが私に声をかけてくれたのです。その人は初老の、紳士然とした男性で、ゼッケンの国籍欄にはFRANCEの文字がありました。声をかけてくれたといっても、その時の私には彼の話すフランス語が理解できなかったのですが、彼はどうやら「水を飲め、一緒に走ろう。」と言っているようでした。彼に励まされ、私は再び走りだすことができました。そうして結局、彼はその日のゴールまで私のことを気遣いながら併走してくれたのです。道中、初めてのフランス語に触れた私はなんとか片言の英語で彼との会話を試みたのですが、あまり上手くいきませんでした。その時、フランス語の簡単な挨拶だけでも勉強しておけばよかったと激しく後悔したのですが、ただ、彼の方は終始鼻歌を歌っていて、そんなことはちっとも気にしていないようでした。サハラマラソンのランナー達は、どこか通じるものがあります。日本から参加していたメンバーとは話が合い、直ぐに仲良くなれました。ならば、あの陽気なフランスの男性とも、もしも私があの時彼が話す言葉を話せていれば、何事かを語りえたはずです。そしてそのように考えると、せっかくのかけがえのない、大切な機会を取り逃してしまったように感じたのでした。 そして今まで、フランス語を短い期間ながらも学習してきた現在になって思うことは、語学を始めるのに「遅い」ということはないということです。私は、物事の「縁」というものを信じています。なにかに強く心惹かれるのなら、それは必然的な文脈の上でそうなっているのだと感じますし、そしてそういった「縁」を感じて何かに夢中になるタイミングというものは、「遅い」とか「早い」とかといった言葉でくくることはできないようにも思うのです。それはあたかも、人間の意図というものとは無関係に、向こうの方からある時突然やってくるかのようです。あの砂漠のレースでの出会いに「縁」を感じた私は、フランス語の世界にどんどん夢中になっていきました。そうして情熱を持って学習していくにつれて、見える世界がどんどん変わっていくのを実感していったのです。例えば、街中には思いがけないほど多くのお店がフランス語の店名を掲げています。聞き覚えのある数々の曲が、実はフランスの歌手が歌うシャンソンであることに気付いた時は、驚きもしました。そして理性的な言語によって紡がれる、フランス哲学の精緻な論理の美しさには目もくらむほどです。フランス語を学び始めて出会った多くの本や音楽、フランスに特有の「理性」の精神は、間違いなく私の生活を豊かにしてくれました。
そして今まで、フランス語を短い期間ながらも学習してきた現在になって思うことは、語学を始めるのに「遅い」ということはないということです。私は、物事の「縁」というものを信じています。なにかに強く心惹かれるのなら、それは必然的な文脈の上でそうなっているのだと感じますし、そしてそういった「縁」を感じて何かに夢中になるタイミングというものは、「遅い」とか「早い」とかといった言葉でくくることはできないようにも思うのです。それはあたかも、人間の意図というものとは無関係に、向こうの方からある時突然やってくるかのようです。あの砂漠のレースでの出会いに「縁」を感じた私は、フランス語の世界にどんどん夢中になっていきました。そうして情熱を持って学習していくにつれて、見える世界がどんどん変わっていくのを実感していったのです。例えば、街中には思いがけないほど多くのお店がフランス語の店名を掲げています。聞き覚えのある数々の曲が、実はフランスの歌手が歌うシャンソンであることに気付いた時は、驚きもしました。そして理性的な言語によって紡がれる、フランス哲学の精緻な論理の美しさには目もくらむほどです。フランス語を学び始めて出会った多くの本や音楽、フランスに特有の「理性」の精神は、間違いなく私の生活を豊かにしてくれました。 私は、思い切ってフランス語の世界に飛び込んで、本当に良かったと断言できます。そして、それは例え私が50歳からフランス語を始めようが、70歳から始めようが同じように満足したとも思うのです。それは、「知る喜び」というものはそれを求める人間の年齢に関係なく、誰の前にも開かれているということを常々感じるからです。
私は、思い切ってフランス語の世界に飛び込んで、本当に良かったと断言できます。そして、それは例え私が50歳からフランス語を始めようが、70歳から始めようが同じように満足したとも思うのです。それは、「知る喜び」というものはそれを求める人間の年齢に関係なく、誰の前にも開かれているということを常々感じるからです。 仏検では、準2級以上のレベルになると書き取り問題が登場します。一次試験において最も配点の高い設問ですから、この問題で高得点を獲得するのが合格への鍵だといえるでしょう。しかし、ただ漫然とフランス語の「音」を聴いているだけでは、書き取りの力は身に付きません。それではどのような点に気をつけながら学習すればよいのでしょうか。
仏検では、準2級以上のレベルになると書き取り問題が登場します。一次試験において最も配点の高い設問ですから、この問題で高得点を獲得するのが合格への鍵だといえるでしょう。しかし、ただ漫然とフランス語の「音」を聴いているだけでは、書き取りの力は身に付きません。それではどのような点に気をつけながら学習すればよいのでしょうか。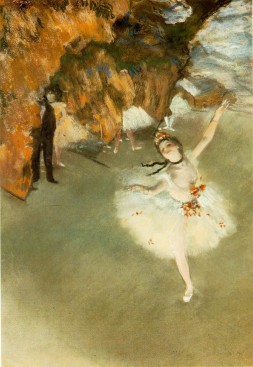


 社会人になって新しいことを学ぶということは、時間の面でもいろいろと制約があり難しいことではありますが、心の中にひとつ新しい芽が生えたような、フレッシュな気持ちになれます。現在は3級取得に向けて勉強中ですが、目下の目標は2級を取得し、フランスに短期留学をすることです。最終的には大好きなフランス文学を、原文で楽しめるようになれれば・・・と夢見ています。
社会人になって新しいことを学ぶということは、時間の面でもいろいろと制約があり難しいことではありますが、心の中にひとつ新しい芽が生えたような、フレッシュな気持ちになれます。現在は3級取得に向けて勉強中ですが、目下の目標は2級を取得し、フランスに短期留学をすることです。最終的には大好きなフランス文学を、原文で楽しめるようになれれば・・・と夢見ています。 電車の中で分厚い紙の辞書の例文を頭の中で音読しながら頭に叩き込むのも効果的であるように感じます。紙の辞書特有の「芳醇な香り」を愉しみつつ…そう、やはり外国語学習は五感を総動員して味わうものですね。特に「文化」の香りが豊かなこの言語は、自分の生活に彩りを加えてくれます。
電車の中で分厚い紙の辞書の例文を頭の中で音読しながら頭に叩き込むのも効果的であるように感じます。紙の辞書特有の「芳醇な香り」を愉しみつつ…そう、やはり外国語学習は五感を総動員して味わうものですね。特に「文化」の香りが豊かなこの言語は、自分の生活に彩りを加えてくれます。 あるいは、ルイ・マル監督『地下鉄のザジ (Zazie dans le Métro) 』に登場するガブリエル叔父さんの暮らすアパートの前で写真を撮ったり…Bonne Nouvelle界隈も50年前の雰囲気をそのまま残し、映画の舞台にタイムスリップしてきました。
あるいは、ルイ・マル監督『地下鉄のザジ (Zazie dans le Métro) 』に登場するガブリエル叔父さんの暮らすアパートの前で写真を撮ったり…Bonne Nouvelle界隈も50年前の雰囲気をそのまま残し、映画の舞台にタイムスリップしてきました。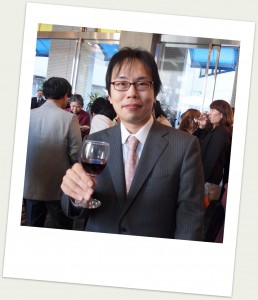




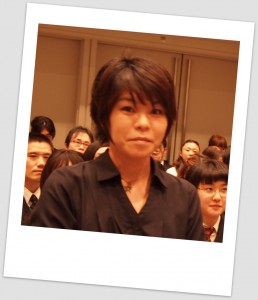

 そこで、大学進学までに3級まで取得することを目標に勉強を開始しました。大学受験勉強開始時期と重なったり、高校の授業や部活もあって、あまり時間が無かったのですが、それらを両立させながらこの検定に関わる様々な問題集を使って独学を始めました。
そこで、大学進学までに3級まで取得することを目標に勉強を開始しました。大学受験勉強開始時期と重なったり、高校の授業や部活もあって、あまり時間が無かったのですが、それらを両立させながらこの検定に関わる様々な問題集を使って独学を始めました。 大学2年生の夏、幼いころから夢だったフランス留学を実現し生きたフランス語に触れ、帰国後は力試しで準2級を受験し、合格。そして成績優秀者として表彰いただいて、嬉しい限りです。今後もさらに上の級の取得、語学力向上を目指してフランス語に磨きをかけたいと思っています。
大学2年生の夏、幼いころから夢だったフランス留学を実現し生きたフランス語に触れ、帰国後は力試しで準2級を受験し、合格。そして成績優秀者として表彰いただいて、嬉しい限りです。今後もさらに上の級の取得、語学力向上を目指してフランス語に磨きをかけたいと思っています。 2010年に定年退職後、これからは趣味のテニス三昧と思っていましたが、日本の高齢化社会についての情報を見るにつけ、体だけ丈夫なおばあちゃんじゃまずい!何か脳を刺激することをやらなくては!と思うようになりました。一生楽しく続けられて、脳全体を活性化するもの、そして新しい人生の小窓を開けてくれるもの、色々探してその条件にぴったりなフランス語の勉強を再開することにしました。
2010年に定年退職後、これからは趣味のテニス三昧と思っていましたが、日本の高齢化社会についての情報を見るにつけ、体だけ丈夫なおばあちゃんじゃまずい!何か脳を刺激することをやらなくては!と思うようになりました。一生楽しく続けられて、脳全体を活性化するもの、そして新しい人生の小窓を開けてくれるもの、色々探してその条件にぴったりなフランス語の勉強を再開することにしました。

 もう、30年以上も前から、姉は教育テレビのフランス語講座をよく見ていました。一緒に暮らす私も時々横から覗いていましたが、なにしろ基本を全く知らないので、「今日のスキットは面白かった」って言っても、ただそれだけです。そんな形のフランス語との付き合いが長く続いていたのですが、ついに決断したのです。心を入れ替えて本気で勉強しよう!!と。
もう、30年以上も前から、姉は教育テレビのフランス語講座をよく見ていました。一緒に暮らす私も時々横から覗いていましたが、なにしろ基本を全く知らないので、「今日のスキットは面白かった」って言っても、ただそれだけです。そんな形のフランス語との付き合いが長く続いていたのですが、ついに決断したのです。心を入れ替えて本気で勉強しよう!!と。 私のフランス語学習まだ、スタート地点に立ったばかりです。この先、山あり谷ありの険しい道が待っていることでしょう。でも、60代は学習適齢期だと思っています。自分の時間がたっぷり持てるし、それに、気力、知力ともに充実して、やる気満々ですから。巷には、勉強大好きな60代が溢れています。私もこの貴重な時期に、様々な知識を吸収し、学び続けることが、先々の習慣になるようにと願っています。
私のフランス語学習まだ、スタート地点に立ったばかりです。この先、山あり谷ありの険しい道が待っていることでしょう。でも、60代は学習適齢期だと思っています。自分の時間がたっぷり持てるし、それに、気力、知力ともに充実して、やる気満々ですから。巷には、勉強大好きな60代が溢れています。私もこの貴重な時期に、様々な知識を吸収し、学び続けることが、先々の習慣になるようにと願っています。  私は小さな頃から、何歳のときからかは覚えていませんが、気づいた時には「フランス語を勉強したい!」と思っていました。確かなことは15歳のときに初めて訪れた国際空港でエールフランスのカウンターを見つけ、乗りもしないのにそこで記念撮影をしたこと。あの時にはすでにフランスに対して漠然とした憧れを抱いており「いつかこの飛行機に乗って、フランスに行くんだ!」と強く思ったことをはっきりと覚えています。
私は小さな頃から、何歳のときからかは覚えていませんが、気づいた時には「フランス語を勉強したい!」と思っていました。確かなことは15歳のときに初めて訪れた国際空港でエールフランスのカウンターを見つけ、乗りもしないのにそこで記念撮影をしたこと。あの時にはすでにフランスに対して漠然とした憧れを抱いており「いつかこの飛行機に乗って、フランスに行くんだ!」と強く思ったことをはっきりと覚えています。 旅行でフランスへ行くことと実際にそこで生活することとの間には大きな差があり、渡航当初は戸惑うことも多々ありました。しかし、段々とフランス人の友達の助けがなくても自分のフランス語だけで出来ることが増えていき、そういう小さな成功の積み重ね、それは「ひとりで銀行に行って口座に関する問題が解決できた」や「スムーズにレストランの予約が取れた」など本当に些細なものでしたが、全てが自信につながり、留学生活が楽しめるようになっていきました。
旅行でフランスへ行くことと実際にそこで生活することとの間には大きな差があり、渡航当初は戸惑うことも多々ありました。しかし、段々とフランス人の友達の助けがなくても自分のフランス語だけで出来ることが増えていき、そういう小さな成功の積み重ね、それは「ひとりで銀行に行って口座に関する問題が解決できた」や「スムーズにレストランの予約が取れた」など本当に些細なものでしたが、全てが自信につながり、留学生活が楽しめるようになっていきました。 在学中から、将来はフランス語を使った仕事をして活躍したいと思っていましたが、自分の語学力がまだまだ足りないと感じ、昨年卒業後から今までの約1年間、語学学校(アテネフランセ)で徹底的に勉強しました。準1級に合格するためには文法・読解など全ての要素を全体的に底上げしなければならないと思い、基礎からやり直しました。
在学中から、将来はフランス語を使った仕事をして活躍したいと思っていましたが、自分の語学力がまだまだ足りないと感じ、昨年卒業後から今までの約1年間、語学学校(アテネフランセ)で徹底的に勉強しました。準1級に合格するためには文法・読解など全ての要素を全体的に底上げしなければならないと思い、基礎からやり直しました。 大学院などに所属しているわけではないので、自分の不安定な立場に心折れそうになったこともありましたが、合格するくらいの力がつけば、必ず道は拓けると信じていました。そして今、目標を達成したことにより、フランスの大学院への進学挑戦などを含めた、また次の目標を設定することが出来そうです。今後もさらなる高みを目指し、努力し続けたいと思います。
大学院などに所属しているわけではないので、自分の不安定な立場に心折れそうになったこともありましたが、合格するくらいの力がつけば、必ず道は拓けると信じていました。そして今、目標を達成したことにより、フランスの大学院への進学挑戦などを含めた、また次の目標を設定することが出来そうです。今後もさらなる高みを目指し、努力し続けたいと思います。 Des jeunes salariés ou des retraités? Des Tokyoites ou des provinciaux?
Des jeunes salariés ou des retraités? Des Tokyoites ou des provinciaux?


 私はフランスは勿論海外渡航全くの未経験者です。小学校からフランス系カトリック校に通っており、そこでフランス語やフランスの文化に触れる機会があり、フランスは私にとってまだ見ぬ憧れの国となりました。中学ではフランス語と英語のどちらかを選択するシステムの為、私はフランス語を選択し、中学からようやく本格的な勉強が始まりました。
私はフランスは勿論海外渡航全くの未経験者です。小学校からフランス系カトリック校に通っており、そこでフランス語やフランスの文化に触れる機会があり、フランスは私にとってまだ見ぬ憧れの国となりました。中学ではフランス語と英語のどちらかを選択するシステムの為、私はフランス語を選択し、中学からようやく本格的な勉強が始まりました。



 毎回、約10分程度の動画、学生をモデルにしたファッション用語スライド、先輩学生が作成したレポート、フランスで出版されている MANGAのファッションに関わる場面の抜粋など、とにかく短時間で数多く見せる。
毎回、約10分程度の動画、学生をモデルにしたファッション用語スライド、先輩学生が作成したレポート、フランスで出版されている MANGAのファッションに関わる場面の抜粋など、とにかく短時間で数多く見せる。