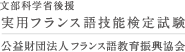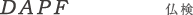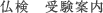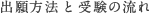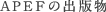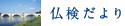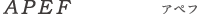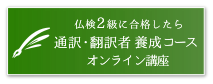高校におけるフランス語教育の現場から ~「ここ」と違う世界を学ぶ喜びのために~
林 宏和 (北海道札幌国際情報高等学校・立命館慶祥高等学校)
90年代、パリ滞在中のこと。
よくモンパルナス界隈で、フランソワ・トリュフォーの映画でおなじみの俳優、ジャン=ピエール・レオを見かけていた。当時、ある雑誌の仕事をしていた私は、彼にインタヴューをすることを思い立つ。レオ氏がよく出没するというカフェの主人から彼のアパルトマンの在り処を聞き出し、直接交渉へ。鉄製の重い扉を何度かたたく。すると、夕方にもかかわらず、ボサボサ頭で下着姿のレオ氏本人が顔を出す。私が、突然の訪問をわびながらも、用件を話すと、彼は「郵便箱に連絡先を残せ」という。アパルトマンの入り口に住人たちの郵便箱が並んでいた。その中にひとつだけ、なぜか“ふた”のない箱があり、手書きで彼の名が書かれている。私は不安な面持ちでメモを残す。それでも、期待に胸はふくらんでくる。そして、まるで『ママと娼婦』の舞台であるアパルトマンを垣間見て来たような気分にとらわれる。
やがて、その晩、家に電話がかかってくる。
「ワタシはジャン=ピエールの友人だ。彼は今パリにいないんだよ。君のメモは渡しておくよ。とりあえず、インタヴューの件はまたにしてくれ、、、」
「ちょっ、ちょっと待ってください。僕はついさっき、彼に直接あったはずですが、、、」
「いや、それは違うんだよ。とにかくそういうことなんだ」
電話はあっけなく切られてしまった。絶句とはまさにこのことだ。しかし、次の瞬間、笑いがこみ上げてくる。むふっという笑いが、、、なぜなら、その、妙に低く、不自然に作られた電話の声はジャン=ピエール・レオ自身のそれだったのだから、、、思えば、映画のなかの彼もよく電話口で声を変え、言い訳をしていたっけ、、、私はいつのまにか彼の映画の世界に引きずりこまれていたというわけだ。
これは、私が授業を担当するクラスで話すエピソードの中の一つである。
高校でフランス語を教えることには、ある面白さがある。
高校生たちが普段学んでいる教科はその多くが大学入試と関連しているのに対し、フランス語をはじめとする第二外国語は入試という出口を持たない。(もちろん、センター試験等をフランス語で受験するということもありうるが、多くの高校では、現在のカリキュラムで受験レベルまで教えることは不可能だ。)
すると、入試科目の学習は彼らにとって「義務」であり、学びの先に目的があるが、フランス語の場合は学ぶことが「権利」であり、それ自体が目的になりうる。入試科目でないフランス語だからこそ、高校生たちは、日々の授業の中で「学びの喜び」を発見しやすいように思える。そして、私は、その喜びの積み重ねによって、大学でもフランス語学、フランス文学を専攻しようという意志をもつ生徒を見てきたし、専門という形ではなくても「フランス」という他者を意識していく生徒を輩出してこれたと思う。目的が「学び」を義務づけるのではなく、「学び」から目的が生まれるのだ。
それでも、一方では、難しさが伴う。私はこの「学びの喜び」を喚起することこそが教育だと思っている。しかし、この点において、私はあるクラスでは成功することもあれば、別のあるクラスでは失敗してしまう。同じことを同じように教えても、また、上記のエピソードをはじめ、同じエピソードを伝えても、クラスによって全く反応が違う。盛り上がることもあれば、シーンと静まり返ることもある。積極的に会話練習に参加するクラスもあれば、そうでないクラスもある。また、一つのクラスでも、日によって生徒の授業への参加度が異なる。だから、教師にとっては、生徒の目を開かせようとする、悪戦苦闘の日々が続くことになる。
そこで私は考える。この日本という国の教育、社会、家庭はあまりに偏差値主義、大学実績主義に傾いてきた。そのすべてが悪いとは思わない。しかし、それは、要領よくテストの点を取りさえすればよいという姿勢を生徒に身につけさせてることには“成功”したが、「学びの喜び」に対する感受性を鈍らせてしまったのではないか?
私はここで制度的な改革を論じようとは思わない。それは検討されるべき問題だが、その実現を夢見る以前に、教師は日々、教壇に立ち続けなければならないからだ。
そこで、あらためて教師とは何かを問いたい。教師の仕事場は教室だ。この場こそがまさに大事だと思う。ここで教師は生徒の前に立ち、声を伝える。それは生徒の耳に届き、そして、「そうか」「そうなの?」という反応を引き起こす。聞く力、受け取る力、そして考える力を育てること、それが教師のしごとだ。教師には伝えたいことがある。それは、「ここ=教室」とは違う世界のことだ。自身が取り憑かれて一生をかけてつきあっていこうとする世界、フランス語の世界のことだ。自分が「すごい」「面白い」と感じていることを伝える。生徒の側に、「ここ=教室」とは違う世界について学び、想像し、それとつながっていこうとする意志を育てることが、フランス語教師の使命である。しかし、これは難しい。生徒のいる地点とは別の世界を扱っているのだから。だから、教師は「本気」でなければならない。「本気」の姿が生徒の目を開かせる。その力を私は信じたい。
教師が一人の生徒と向き合う時間はわずか1年か2年。教室で教える初級フランス語では満足に会話する力、読む力は育てられない。しかし、それでいい。なぜなら、ひとたび目を開いた生徒の「学び」は持続していくからだ。私は、高校のひとつの教室が「ここ」とは違う世界とつながること、そして自分が生徒にとって「学びの喜び」への窓口になれることを願っている。