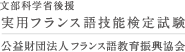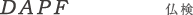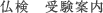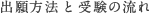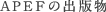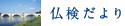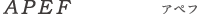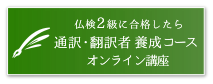外国の学校との交流授業
立花 英裕 (早稲田大学教授)
最近、visioconférenceによって海外と交流授業を行なっている。いわゆるテレビ会議によるフランス語授業である。一般の学習者は、実際にフランス語を話す機会になかなかめぐまれない。いかに教師が実践的なフランス語教育を唱えても、学生が学んだことを生かせる機会が限られているのであれば、その意義は減じてしまう。そこで、教室内に実践の場を作ってしまおうと考えた次第である。
導入したのは、早稲田大学のオープン教育センターで開講されているフランス語上級クラスにおいてである。オープン教育センターの授業は、全学部の学生が登録できる。登録定員は20人に限定した。抽選で落ちた学生が相当数出たがいたしかたなかった。この形態の授業には20人が限度である。
授業形態は、いろいろ考えられるだろうが、一つのポイントは、どこの、どのような学校と提携するかである。そこで私が参考にしたのは、昔のフランス夏期講習での経験である。まだ思うようにフランス語が話せない段階では、フランス人よりも外国人の方が仲良くなりやすいことを思い出した。そこで、まずフランス・ブレストの語学学校CIELに声をかけた。大学の方が通りがいいが、あえて語学学校を選んだ。次に、韓国の仁荷大学Université Inhaとルーアン大学と交渉した。ルーアン大学の場合は、FLEのマスターに在籍している大学院生が相手だったので事情は異なるが、他の2校とは期待通り、外国人フランス語学習者との交流になった。仁荷大学の場合は、もちろん韓国の学生たちが相手で、CIEL校はタイの学生だった。
交流では、双方の学生が料理のレシピを紹介することにした。食は誰でも関心がもてるし、表現が比較的単純である。また、食材を切ったり、フライパンを扱ったりする真似をしなければならないことにしたので、動作と言葉を結びつける練習になる。一回の交流は約60分を目処とした。1人の発表者が、3分から5分程度でレシピを紹介し、質問を受ける。次に、相手校の番になる。やってみると、双方から質問が続出し、毎回予定を大幅に越えて2時間近く授業することになった。今後は、もっとコンパクトにまとめるように努力したい。
授業運営のポイントの一つは、教師の役割である。理想からいえば、学生が主体になってほしいわけで、教師は、様子を見ながら、アドヴァイスを与える程度がいいのだろう。しかし、実際には、継続的に毎週同じ相手と話すなら別だが、1セメスターで1回から3回程度しか顔を合わせない学生同士が対話を維持するには、教師も一定の役割を担う必要がある。たとえば、相手の質問が分からなかったらどうするのか、あるいは、説明が相手に理解してもらえなかったときどうするのかなど、様々な状況に出くわす。今回私は、ある程度、介入することにした。ただし、日本語は使わない。遠隔授業で大事なのは、相手校の教師との間の十分な信頼関係である。相互に信頼できれば、多少のことがあっても乗り切れる。
学生が選んだ料理は、お好み焼き、カツ丼などなど....。韓国の学生は、韓国料理を紹介してくれた。日本の学生もキムチ料理など韓国料理に馴染んでいるので、双方から笑いがわき起こった。フランス料理なら、こうはいかないだろう。CIEL校のタイ人の学生たちは、フランスの大学に入学するために勉強していたので、レベルが遥かに上だった。レベルが均質でないときは、教員が助け船を出してあげる必要がある。そうでなければ、相手が退屈してしまうだろう。相手方も楽しめるように、教師が臨機応変にコメントや情報を与えてやると、次の回の雰囲気も盛り上がるようである。文化的な要素を積極的に取り入れて、教師だからこそできる話をした。タイ人の発音は独特で学生には聞き取りにくかった。しかし、そういうフランス語の発見も、visioconférenceだからこそできる。
遠隔交流授業の利点でもっとも貴重なのは、他者性の体験である。たとえば、こちらの学生が、生卵をご飯にかけて食べる話をしたときのことだ。タイの学生たちが、一様に驚きの声をあげた。「病気にならないか」と、目を丸くした女子学生もいた。このような時、学習者は、普通の授業では学べない何かを体験する。そこには、異文化を「理解」するということには収斂しきれない何かがある。それを他者性の体験と呼んでおきたい。今回の場合は、発表者の語学力があまり高くなく立ち往生したので、教師が引き取ってあげた。とっさにリービ英雄の小説『星条旗の聞こえない部屋』が生卵を食べる行為で終わっていることを思い出したので、その話をした。
実践的な場で学生たちの力は目覚ましく向上していく。文法的な間違いは直さない方がいいようだ。その中で、学生の感応力をいかに引き出してあげるか、それをこれからも模索していきたい。
ツイート