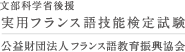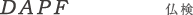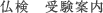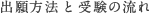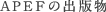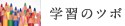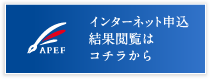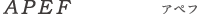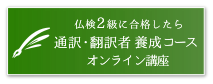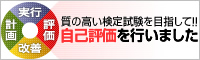四半世紀の時を超えて
2024年春季1級合格・在日スイス大使館賞
岩月 真也
留学先としてはいくつか候補があったのですが、なんとなく「フランス語が話せたらかっこいいかも」という不純な動機でフランス留学を決めた記憶があります。

はじめは当然コミュニケーションがうまく取れず苦労しました。初日に学校の食堂で、一人でさみしく昼食を食べたことは今でも鮮明に覚えています(当時フランスの学校の食堂では決して一人で食事をすることはありませんでした)。 しかし2日目、クラスの女の子3人組が一緒に食事しないかと誘ってくれ、以降毎日その3人組と食事をするようになりました。
彼女たちとは食事以外にも、休み時間に他愛もないことを話したり、それぞれの家に招いてくれたりと、私のフランス滞在の中で大きな存在となりました。
ホストファミリーにも恵まれ、良好な関係を築くことができました。
1年間という短い期間でしたが、周囲の支えもあり本当に充実した留学生活を送ることができました。 さて、私が現地で実践した勉強法は「調べて使う」というサイクルを確立することです。
当然ながらすべてフランス語で会話をするわけですから、1日のうちに言いたくても言えないことなどが出てきます。それをノートに記録し、夜辞書で調べます。そしてその表現を翌日、なんとしても使ってみる。
このサイクルを繰り返してさまざまな表現を覚えると同時に使えるようになっていきました。
外国語は覚えただけでは不十分で、使いこなすことができるようになるまで訓練することが必要です。それを毎日意識して実践していたので、半年後にはある程度のコミュニケーションは取れるようになっていたと思います。 また、現地でしっかり文法を自習したことも、フランス語能力の向上のために必要なことだったと思います。
「通じればいい」という意識を捨て「どうせならちゃんとしたフランス語を話したい」と常に考えていました。
また文法をしっかり学習することにより、必然的に他の言語との構造の違いを意識するようになりました。フランス語の文法はたしかに複雑な面も多いと思います。
しかし、フランス語話者も日本語話者も、同じ人間なのですから、なにもフランス語話者だけが特別だということはないはずです。言語の違いはあれど、そこには血の通った人間が常にいることを忘れてはならないことを、1年間の留学を通して学ぶことができました。
 帰国後、大学大学院で言語学を専攻し、さまざまな言語の構造を調査してきました。そして今では僭越ながら、フランス語を教える立場に立たせていただいています。
しかし、仏検1級を取得した今でも分からないことだらけです。
帰国後、大学大学院で言語学を専攻し、さまざまな言語の構造を調査してきました。そして今では僭越ながら、フランス語を教える立場に立たせていただいています。
しかし、仏検1級を取得した今でも分からないことだらけです。
数年前、初対面のフランス人と会話をしたときのことでした。初めましてのあいさつをし、2,3分フランス語で会話をしました。
するとそのフランス人からこんな質問を受けました。「日本語には冠詞がないのかい?」と。
これはつまり、私のフランス語の冠詞の使い方がまずく、それがたった数分の会話で見抜かれてしまったわけです。
ある程度フランス語会話には自信があったのですが、この体験をきっかけに、まだまだやるべきことはたくさん残っていると思わされたのでした。 言語学習に終わりはない。これからも一生勉強は続くと思います。 ツイート